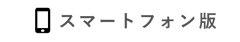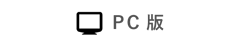アンティーク家具の
修理・修復について
ひとつひとつの個性と
大切に向き合います。
Antiques *Midiでは、アンティークならではの風合いや魅力はそのままに
実用的に問題なくご使用いただけるよう、
全ての家具のメンテンスを販売前に行っております。
一言でメンテンスと言っても、基本的に一点ものであるアンティーク家具は
デザインがそれぞれに異なるのはもちろんのこと、
構造や材質、使われてきた年数、環境なども異なり
修理方法もそれぞれに異なります。
Midiでできる
メンテナンスのこと
経験豊富な職人がそれぞれの家具の状態を見極め、
それぞれに適した修理を一点一点丁寧に行っています。
普段なかなかお見せする機会のない
*Midiの裏側のシーンを、各工程ごとに少しご紹介しますね。
木工
長く使ってきた家具はどうしても、時間の経過とともに緩みが生じてしまいます。他の家具と比べても負担がかかりやすいチェアは、緩みが生じやすい家具の一つです。ファブリックチェアであれば、まず元々の生地を剥がしフレームだけの状態にした上で、一度全てのパーツをバラバラにします。強度が保てない部分はパーツごと交換する場合もあり全てのパーツが揃ったところで、組み直しを行います。強度を上げるため、膠 ( にかわ ) と呼ばれる接着剤を接続部分に刷毛で塗り、ゴムバンドやクランプを使って固定していく作業。膠はおよそ30分ほどで硬化します。テーブルもチェアと同様に基本的に組み直しを行います。箱もの家具は、ものによっては組み直しを行う場合があります。
パーツ製作
アンティーク家具の装飾部はとても繊細。
さらに100年もの年月を重ねているのですから完全な状態で残っている方が褒むべきこと。パーツが片方だけ無くなっている、折れている、欠けているものも中にはどうしてもありますが、それだけで価値を失ってしまうものではありません。元の姿に蘇らせる確かな技術もここにあります。新しいパーツの製作には、まずノギスで玉の大きさやピッチなど採寸し図面を作成します。旋盤を使い、ノミを当てて丁寧に木材を削り出しオリジナルのパーツの形に段々と近づけていきます。まさに職人の技術が問われる繊細な作業です。最後に着色をし、エイジングを施し、時代を合わせていきます。
椅子の張り替え
椅子の組み直しが完了したら、次は生地を張っていく作業。こちらも熟練の職人がひとつひとつ手作業で仕上げていきます。
古い椅子の内部は束土手を作り馬毛などが詰められていることが多いですが、現在は衛生上の理由もあり、ウレタンに変えることがほとんどです。ソファやアームチェアなど座面の大きなものは、バネを吊り、より強度が高く弾力のある仕様に。生地を張り終えると、最後に縁をテープや鋲で仕上げていきます。特に単鋲は、ひとつひとつ打ち込んでいくので大変な手間と技術が必要とされる作業です。
チェアを張り替える過程で、*Midiが特にこだわっているのが、見た目の美しさと座り心地のよさ。形、高さ、かたさをとても重視していて、職人と何度もやりとりをして現在のような理想の形が出来上がりました。
ガラス・ミラー交換
窓やドア、キャビネットの扉にはめ込まれている古いガラスは独特のゆらゆらとした表情を持ち現代まで残っていることはとても希少ですので状態が良ければ古いものをそのまま使用しますが、ガラスもパーツと同様に年月の経過によりヒビが入ったり、割れてしまっていることもあります。その場合は新しいガラスに交換します。
ミラーも同様に、割れているものや汚れやシミが多く実用が困難なものは、新しく交換します。サイズを測り、ガラス専用のカッターで切り出し枠にはめ込みます。キャビネットなどのガラスは木枠で留めることが多く、扉や窓などのガラスは、ガラスを留める専用の金具を打って、パテで仕上げるのが昔ながらの手法。現在は金具の代わりにコーキングを施しパテで仕上げる場合やコーキングのみで仕上げる場合もあります。伝統的な手法を大切しながらも、現代の需要や状況に合わせ、修理方法も日々試行錯誤しています。
金具取り付け
剥離や塗装など、家具の表面に手を加えるメンテ ナンスに入る前には必ず取手や鍵プレートなど元々付いていた金具を一度取り外します。全ての作業を終えたら、最後に金具を元の場所に戻して完成です。基本的には元々付いていたパーツをそのまま戻しますが、パーツに欠損などがある場合には、雰囲気の合うアンティークの取手を新たに選んで取り付けることも。またアンティークの古い鍵は、硬くて回らなかったり、すでに機能していないこともあります。その場合は、扉にローラーキャッチなど、新しい金具を取り付けることもあります。
塗装
テーブルやサイドボードの天板など必要に応じて再塗装を行うことがあります。輪じみが付きやすいテーブルなどは、扱いやお手入れが簡単な吹き付けのウレタン塗装 ( 油性ウレタン ) で仕上げます。まずは、剥離剤と呼ばれる薬品を使って古い塗装を落としていきます。剥離剤を刷毛で塗り、反応が出たところでスクレーパーで削ぎ落としていきます。塗装が剥がれたらシンナーで拭き取り、サンダーを使ってサンディング。中塗り ( サンディングシーラー ) と呼ばれる吹き付け塗装を一度行い、もう一度サンディング。手間のかかる作業ですが、この工程がとても大切。最後に仕上げのウレタン塗料を吹き 付けて完成です。ウレタン塗装は、表面に厚い塗膜ができるため、汚れやシミ、水気に強く、傷も付きにくいというメリットがあります。色合いや艶感を調節しやすいのも特徴です。
仕上げ
上記の塗装 ( 吹き付けのウレタン塗装 ) の他にも様々な仕上げ方法があります。まずステインを塗り、さらにシェラックニスを何度も重ね塗り、最後にワックス仕上げ。ワックスも定期的に塗る必要性があり、少しお手入れが大変ですが、昔ながらのスタンダードな仕上げ方法です。他にも、木本来の風合いはそのままに保湿の役目を果たしてくれ、少ししっとりとした質感を生むオイル仕上げ。油性ウレタンには劣りますが、比較的耐久性の高い水性のウレタン仕上げ。色落ちしやすいペイント家具には、色落ちを止める効果のあるラッカーで仕上げることも。素材の良さを活かし、尚且つ問題なくお使いいただけるよう家具によって、様々な仕上げ方法を使い分けています。
がたつき確認
家具のメンテナンスが全て完了したら、水平を測る専用の大きな分厚い鉄板に乗せ、最後にがたつきを確認します。当店で販売している家具は全てこの工程を行っています。がたつきがあった場合は、サンダーで脚の裏を少し削り微調整していきます。テーブルや箱もの家具は、水平器を使って、天板にも歪みや傾きがないか確認しています。家具を設置される場所や環境によっては ( 例えば、無垢のフローリングなどで床が完全なフラットでない場合 ) 多少のがたつきが生じる場合もございますので、チェアやテーブルなどには脚先に貼るフェルトもおつけしております。
照明の修理
照明類は基本的にコードやソケットを日本規格の新しいものに交換しているので安心してお使い頂けます。日本規格の電球を使用することができ、LED電球もご使用いただけます。( 構造上交換ができないものに関しては、安全点検を行った上、海外の古いソケットをそのまま使用することもありますが、コードは全て交換しています。) 自社で修理を行っておりますので、コードを短くしたい、長くしたい、コンセント仕様に変えたいなどのお客様のニーズにも、迅速に柔軟に対応することができます。
重量が5kg以下の照明には引っ掛けシーリングも取り付けておりますので、配線工事は不要で、そのままカチッと簡単に取り付けていただくことが可能です。重量が5kg以上の吊り下げ照明、またはウォールランプなどは、直付け配線工事が必要ですので、コードは切りっぱなしの状態でのお渡しとなります。
梱包
当店では、ご注文のお品をお客様のもとへ無事にお届けできるよう細心の注意を払って梱包しています。アンティークのアイテムはとても繊細なものが多く、そのほとんどが一点もので代替品がないため、運送中の破損をゼロにできるよう日々試行錯誤に努めています。大型の家具は、アートセッティングデリバリー” 家財便” にてお届けさせていただいておりますが、( 原則、梱包・輸送・搬入・開梱・設置を一貫して運送業者が行います ) 当店では、梱包を運送業者に任せっきりにせず自社独自の梱包を行い、より強度を高めた状態で引き渡しています。特に繊細なものは木枠を組んで発送することもあります。唯一無二の逸品を選んでくださったお客様に、笑顔で受け取っていただきたいという想いで、毎日心を込めてお包みし、送り出しています。